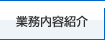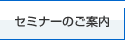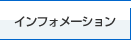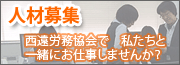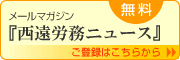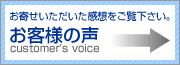3月 10th, 2021
「問題社員対応」をテーマに、Zoomを利用してセミナーおこないました。
参加者の皆様よりいただいた感想です。
・・・
今回のセミナーでは、前にこのような色々なご指導があれば、当社はもっとしっかりした対応ができたのではと今さら思います。これを機会にこれからの採用及びその後の対応に生かしたいと思います。
問題社員対応に関して、色々なケースを挙げてご説明いただいたので、とても良くわかりました。また、具体的な就業規則の作り方なども参考になりました。ありがとうございました。
非常に分かりやすく、タイムリーな内容で有意義でした。全ての子とに、ルール化や規則を定めて、就業規則に盛り込む事が大切だと実感しました。時代に合った就業規則の見直しを早急にすべきだと思っております。
今回のセミナーでは問題社員への対応について学びましたが、学びで終わらせずにこれらのことを実践する勇気が大事かと思います。先ずは記録を残す習慣を付け、時々は見直して社内で何が問題になっているかを把握するところから始めてみます。
具体的に行うべき行動の流れや実際の規定・書面の例、法改正の情報を教えていただき、とても勉強になりました。
コミュニケーション、教育訓練、面談が必要など、対策を具体的に教えて頂き大変勉強になりました。知識を得ると、心が強くなれます。ありがとうございました。
記録に残すとか、就業規則を修正しておくとか、準備が大事だという事がよくわかりました。会社として対応すべきことが多いとは思いますが、記録に残すなど、管理職にも協力してもらわなければならないこともあると思いますので、順次整備を進めつつ、社員にも共有していってもらうことを平行して進めていきたいと思います。
・・・
等々、参加してくださった皆様、ありがとうございました。
Posted in これまでのセミナー | No Comments »
3月 5th, 2021
毎年2~3月に開催しています賃金セミナー、今年はZoomを利用しておこないました。
今年のテーマは、「同一労働同一賃金への対応」と、「「高齢者賃金」でした。
参加者の皆様よりいただいた感想です。
・・・
具体的な数字も絡めてお話しいただいたので、とてもわかりやすかったです。
いつ講義を受けても、大変わかりやすく説明していただき、うれしく思います。
大きな不合理な差がある中、皆が不満に思っていることはないか、世間並みになっているか、考えたいと思います。取り組みやすい部分は、変えていきたいと思います。一番大事なことは、納得できる説明をすることだと思いました。
Zoomセミナーを初めて受講しました。大変聞きやすく、会場よりっもむしろしっかり把握できたように思います。パートさんの諸手当、特に通勤手当の例を示したいただいたのがよかったです。慶弔休暇、手当も参考になりました。
当社は今日のセミナーで推奨しないパターンにあてはまるので、参考にし、改善していきたい。同一労働同一賃金については、定年近い人たちからも問題にする声があがっている。
他研修では聞けないような情報が入手でき、それだけでも受講した価値があります。
等々、参加してくださった皆様、ありがとうございました。
Posted in これまでのセミナー | No Comments »
3月 2nd, 2021
一定の割合で障害のある人を雇用することが義務付けられている「障害者雇用率制度」。
法定雇用率(労働者のうち、障害のある人をどの程度の割合で雇用する必要があるかを定めた基準となる割合)が、R3.3.1から以下のように変わりました。
…
〇民間企業の法定雇用率〇
従来:2.2%
R3.3.1~:2.3%
…
法定雇用率の変更に伴い、障害者を雇用しなければならない企業の範囲も、
従来:従業員数45.5人以上
R3.3.1~:従業員数43.5人以上
へと変わっています。
従業員数が43.5人以上の企業は、毎年6月1日時点の障害者の雇用状況をハローワークへ報告する必要があります。
従業員数によっては今年からは報告が必要、という企業様もでてきますね!
なお、令和2年度分の障害者雇用納付金については、従来の法定雇用率(2.2%)で算定することとなります。
Posted in ぴかっと情報 | No Comments »
2月 24th, 2021
多くの企業様にご利用いただいているキャリアアップ助成金。
その中でも特に利用頻度の高い、「正社員化コース」(非正規の職員を正規雇用等へと転換させ、一定の要件を満たした場合に支給対象となります)について、令和3年度以降、要件が変更されることとなりましたので、概要をご案内させていただきます。
…
〇現行要件〇
正規雇用等へ転換した際、転換等の前の6ヵ月と、転換等の後の6ヵ月の賃金を比較して、以下のア、イのいずれかが“5%”以上増額していること。
ア:基本給および定額で支給されている諸手当(賞与を除く)を含む賃金の総額
イ:基本給、定額で支給されている諸手当および“賞与を含む”賃金の総額(転換後の基本給および定額で支給されている諸手当の合計額を、転換前と比較して低下させていないこと)
…
〇新要件〇
正規雇用等へ転換した際、転換等の前の6ヵ月と転換等の後の6ヵ月の賃金(※“賞与は含めない”)を比較して、“3%”以上増額していること。
…
上記のように、求められる賃金アップ率は5%から3%へと低下しましたが、賃金アップの算定にあたり賞与を含むことができなくなっています。
「これまでと同じように正社員にしたのに、助成金がもらえなかった・・・」
このようなことにならないよう、注意が必要です!
Posted in ぴかっと情報 | No Comments »
2月 15th, 2021
「新型コロナウイルスの影響で前職を離職した求職者の採用を考えている」
そんな企業様にご利用いただける助成金ができました。
…
それは、“トライアル雇用助成金(新型コロナウイルス感染症対応(短時間)トライアルコース)”です。
この助成金は、コロナの影響で離職し、これまで経験のない職業に就くことを希望している求職者を、無期雇用へ移行することを前提にお試し雇用する会社が利用できる助成金です。
トライアル雇用期間中に社員の適性を確認したうえで無期雇用へ移行することができますので、ミスマッチを防ぐことができます。
…
〇対象となる労働者〇
①令和2年1月24日以降に、新型コロナウイルス感染用の影響により離職した
②紹介日時点で、離職している期間が3ヵ月を超えている
(パート・アルバイトなどを含めて、一切の就労をしていないこと)
③紹介日において、就労経験のない職業に就くことを希望している
※上記①~③すべての要件を満たした上で、求職者本人がトライアル雇用を希望する場合に対象となります。
…
〇助成額〇
A:週の所定労働時間が30時間以上の場合:月額最大4万円(最長3ヵ月)
B:週の所定労働時間が20時間以上30時間未満の場合:月額最大2.5万円(最長3ヵ月)
…
この助成金を利用するためには、事前にトライアル雇用求人をハローワークへ提出し、ハローワーク等からの紹介で対象者を雇用する必要があります。
その他、詳細は担当者までお問合せください。
Posted in ぴかっと情報 | No Comments »
2月 10th, 2021
多くの中小企業が加入している協会けんぽ。
毎年春に保険料率の見直しがおこなわれます。
…
令和3年度の協会けんぽ(静岡県)の保険料率は、
健康保険料率:現行(9.73%)⇒令和3年度(9.72%)
と、わずかですが引き下げとなりました。
※40歳から64歳までの被保険者には、これに介護保険料率(1.80%)が加算されます。
…
3月(4月納付分)から令和3年度の保険料率が適用されます。給与計算時は注意が必要ですね。
…
なお、労災保険料率は令和2年度から変更なし、雇用保険料率についても、変更なしとなる見込みです。
Posted in ぴかっと情報 | No Comments »
2月 2nd, 2021
パートや嘱託といった非正規雇用の方の中には、メインのお仕事として自営業を営んでいる方がいらっしゃいます。
こういった方は、これまで、従業員として勤務する会社で雇用保険の適用要件
(一週間の所定労働時間が20時間以上、かつ、31日以上の雇用の見込みがあること)
を満たして勤務していても、従業員としての収入よりも、自営業による収入が多い場合は、雇用保険に加入することができませんでした。
…
しかし、令和3年1月1日以降、会社で働く従業員の方が自営業を営んでいる場合でも、従業員としての労働条件が雇用保険の適用要件を満たす場合は、従業員としての収入と自営業などによる収入のどちらが多いかに関わりなく、雇用保険に加入することとなりました。
…
令和2年12月31日以前から勤務している場合は、令和3年1月1日から被保険者となりますので、資格取得の手続きが必要です。
…
自社でお手続きされている事業所様は、対象者の有無について、一度ご確認ください!
Posted in ぴかっと情報 | No Comments »
1月 22nd, 2021
新型コロナウイルスの影響など、企業環境は大きく変わっています。昇給どころではない会社も少なくありません。その上、中小企業でも4月から「同一労働同一賃金」が適用に。この先どう経営し、どう賃金を決めていったらよいのかとお悩みではありませんか?
限られた原資をいかに効果的に分配し、従業員のヤル気を喚起するかが経営者様の「知恵」の見せどころ。今年はZoomセミナーで、賃金見直しの解決へのヒントや、解決に役立つ情報をご提供させていただきます。
///////////////////
賃見見直しセミナー
■日時:2021年3月2日(火) 13:30~15:30
■開催方法:Web会議システム「ZOOM」利用
■参加費:1名様につき11,000円(税込。顧問先様は無料)
■主催:西遠労務協会
詳しい内容と参加申込書はこちら(PDF。プリントアウトしてファックスしてください)
///////////////////
主な内容
1.同一労働同一賃金
2.定年後再雇用者の処遇
3.その他
Posted in セミナー開催予定 | No Comments »
1月 22nd, 2021
昨年、今年と、企業も個人もコロナウイルスに翻弄されています。中小企業はただでさえ人・モノ・お金に余裕がないことが多い。だからこそ問題社員に関するご相談が増えている印象です。コロナによる休業実施の影響、退職者からの残業代請求、退職代行サービスによる退職申し入れ、ネット掲示板へ会社の評判書き込み、パワハラ被害の訴え等々。古い考え方や常識はもはや通じません。
会社も、社会情勢の変化、社員の意識の変化への対応・対策が必要です。問題社員に対し、具体的にどのような対処法があるのか?また、法律的にはどのような対応ができるのかを理解し、労務トラブルが発生したときに迅速に適切に対応できるようにしておきましょう。今回のセミナーでは、実際の困りごとの事例と対応の仕方の他、就業規則見直しのポイントも解説いたします。
///////////////////
問題社員への対応セミナー
■日時:2021年3月5日(金) 13:30~15:30
■開催方法:Web会議システム「ZOOM」利用
■参加費:1名様につき5,500円(税込。顧問先様は無料)
■主催:西遠労務協会
詳しい内容と参加申込書はこちら(PDF。プリントアウトしてファックスしてください)
///////////////////
主な内容
1.問題社員対応策と就業規則での工夫
2.最近の法改正
3.本日のまとめ
Posted in セミナー開催予定 | No Comments »
1月 19th, 2021
昨年こちらのブログでご紹介させていただきましたように、R3.1.1より、子の看護休暇や介護休暇について、社員から申し出があった場合、1時間単位で取得させることが事業主の義務となっています。
…
〇子の看護休暇〇
小学校就学前の子を養育する労働者が、負傷・疾病にかかった子の世話等をおこなうために事業主に申し出ることにより、1年度あたり5日(子どもが2人以上の場合は10日)を限度として取得できる休暇制度。
…
〇介護休暇とは〇
要介護状態にある対象家族の介護や世話をする労働者が、事業主に申し出ることにより、1年度あたり5日(対象家族が2人以上いる場合は10 日)を限度として取得できる休暇制度。
…
社員が子どもの看護や家族の介護で休みを取得する場合、有給休暇として申請するケースが多いのが実際のところではありますが、子の看護休暇や介護休暇として申し出があった場合、どちらも会社は無給扱いとして処理することが可能です。
しかし、育児・介護休業法では、この看護休暇や介護休暇の取得によって社員に不利益が発生することを禁じていますので、無休扱いでも、欠勤とは別に考える必要があります。
査定時にはご注意を。
Posted in ぴかっと情報 | No Comments »