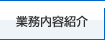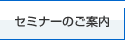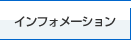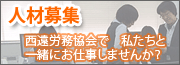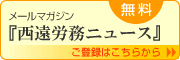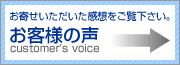1月 17th, 2023
1月から、協会けんぽの届け出様式が変わりました。
傷病手当金の届け出様式も変わったのですが、大きな変化の一つに、「受取代理人」の欄がなくなった、ということがあげられます。
これまでは、本人からの委任により、会社が傷病手当金の「受取代理人」となることも、実務的に可能でした。つまり、会社が立て替えている社会保険料等を、代理で受け取った傷病手当金から控除し、その後本人に振り込む、などということもできたわけです。けれども今後はそれはできなくなり、振り込みは本人に対して、となったのです。
もともと傷病手当金はご本人のものですから、今回の変更は当たり前と言えば当たり前。けれど、この「受取代理人」の欄を利用していた会社は、別の方法で、立て替えた保険料等を本人に支払ってもらう必要が。
本人が病気やケガで休み始める前に、これまで以上に、本人と、ココはしっかり約束しておきましょう。「徴収できなかった!」とならないように。
Posted in カツジンぶろぐ | No Comments »
10月 14th, 2022
西遠労務ニュースでもご案内させていただきましたように、今月から雇用保険料率が引き上げられ、労働者と事業主、それぞれの負担分が増えることとなりました。
…
○10月からの新しい雇用保険料率は?
・一般の事業 労働者負担分:5/1000(旧:3/1000) 事業主負担分:8.5/1000(6.5/1000)
・建設業 労働者負担分:6/1000(旧:4/1000) 事業主負担分:10.5/1000(8.5/1000)
…
例えば・・・
10月分より、月給(総支給額)が30万円である場合の労働者負担分の雇用保険料は、
・一般の事業:300,000×5/1000=1,500
・建設業 :300,000×6/1000=1,800
となります。
…
○なぜ保険料率が上がったの?
雇用保険料は、失業給付や雇用調整助成金の財源となっています。
新型コロナウイルスの影響で、雇用調整助成金の支給額が増え続け、財源不足が課題となったために、雇用保険料率が改定された、と言われています。
※ちなみに、令和3年度だけで、50,898.85億円の雇用調整助成金が支給されたことが発表されています。
…
10月支給給与計算では、新雇用保険料率の適用をお忘れのないよう、ご注意ください!
Posted in ぴかっと情報 | No Comments »
9月 6th, 2022
「改正育児介護休業法」解説セミナー(顧問先様説明会)を、Zoomにておこないました。
今回の目玉は、「パパ育休」。そして、「パパ育休」中に仕事ができるようにすることも可能、という点。
参加してくださった皆様、顧問先様、ありがとうございました。
・・・
参加の皆様から頂いたお声の一部です。
・産後パパ育休中の働き方(働いてもらい方)がわかりました。
・法改正だけでなく、実務として発生しそうなことをプラスして説明してもらえたので、現実的に考えることができました。
・パパ育休中の働く条件・ルールなどがわかりやすかった。
・会社の立場に立って、準備することや対策を説明してもらった。ありがとうございました。
・・・
ご参加の皆様、ありがとうございました。
西遠労務では、今後も、皆様の実務に役立つ説明会を開催してまいります。お気軽にご参加ください。
Posted in これまでのセミナー | No Comments »
8月 5th, 2022
西遠労務協会は、8/11(木)から8/15(月)まで、お休みを頂戴します。
…
皆様にはご不便をおかけしますが、留守番電話にメッセージを残していただけ
れば、折り返しのご連絡をさせていただきます。
…
ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解とご協力を賜りますよう、よろしくお願
いいたします。
Posted in インフォメーション | No Comments »
8月 4th, 2022
今年2月に、R4.4の改正育児介護休業法への対応について、セミナーを開催いたしました。
今回は、R4.10の育児介護休業法改正への対応について、セミナーを企画しましたので、ご案内させていただきます。
経営者様、労務ご担当者様、ぜひご参加ください。
…
…
【説明会の主な内容】
① 10月施行分の法改正の制度解説
② 社会保険料免除の仕組みの変更点
③ 会社がすべきこと
…
…
【会場・開催日時】オンライン(Zoom)開催
令和4年9月2日(木) 13:30~15:00
…
…
【受講料】5,500円(税込) 顧問先様:無料
…
…
あらかじめZoomアプリが使用できる環境であることを確認しておいてください。
当日、トラブル(映らない、聞こえない他)が発生した場合、大変申し訳ございませんが西遠労務協会にての個別の対応はできかねます。
・・・
参加ご希望の方は、西遠労務協会(TEL 053・436・1033)までお電話でご連絡をお願いいたします。
FAX番号をおうかがいし、申込書をファックスさせていただきます。
Posted in セミナー情報 | No Comments »
7月 1st, 2022
「内定の取り消しってできますか?」そんなご質問をいただくことが。
内定者とやり取りするうちに「この採用、失敗だったかな」と感じられたのかもしれません。内定取消の難易度はどの程度なのでしょうか。
・・・
≪始期付解約権留保付労働契約の成立≫
採用が内定している場合、法的には「始期付解約権留保付労働契約」が成立していると解釈されます。
〇始期付:いつから労働契約が開始されるのか、その時期は決まっている
〇解約権留保付:入社までにやむを得ない事由が発生した場合には、会社は労働契約を解約する権利がある
ここでの「やむを得ない事由」とは、「もしも採用前にわかっていたら採用しなかったであろう、社会一般の常識にかなった客観的・合理的理由」です。入社後に教育可能でしょう、とか、業務にそこまでの差しさわりはないだろう、そんなふうに思われる理由では、内定取消はできず、一般の解雇と同じ扱いになってしまうのです。つまり、内定取消の難易度は「大」と言えるでしょう。
・・・
≪会社の対応≫
会社にとって、そして相手にとっても、非常に大きな痛手となってしまう内定取消。それをおこなうのは難しいことを認識 したうえで、後悔しないために、新卒・中途を問わず入社前面接等での能力・経験・健康面の確認を、形だけにならないよう確実におこなっていきましょう。
Posted in カツジンぶろぐ | No Comments »
5月 10th, 2022
このごろ急増しているのが、パワハラについてのご相談。社員が「実はパワハラを受けているんです」と申し出てきた、というもの。そこで西遠労務協会では顧問先様に、特にパワハラを中心としたハラスメント研修をお勧めし、承っています。
・・・
≪目的≫
1.社内のハラスメントを防ぐため
2.今年4月からの「中小企業のハラスメント防止措置義務化」への対応のため
≪内容の例≫
1.管理職向け
・ハラスメントの基礎知識
・パワーハラスメントとは
・パワハラと業務指導の違い
・パワハラ的な言動を行っていないかのチェック
2.全社員対象
・ハラスメントの基礎知識
・あなたがハラスメントを受けないために
・あなたがハラスメントを起こさないために
・ハラスメント?と感じたら
※ 貴社で今問題になっているハラスメントテーマも取り入れ可能です。
≪時間≫
1時間または2時間
※1時間の研修でも、それが大きな一歩・実績になります
≪料金≫
一般企業様料金と顧問先様料金がありますのでお問い合わせください
電話:053-436-1033西遠労務協会 担当:山口悦子(ハラスメント防止コンサルタント)
Posted in カツジンぶろぐ | No Comments »
2月 24th, 2022
改正が続く育児介護休業法ですが、2022年4月・10月にも改正が実施されます。
今回のセミナーでは、4月・10月の改正点のポイントと、この改正に対応するため、会社がいつ何をするべきかをご説明させていただきました。
…
以下、セミナーに参加してくださった皆様からいただいた感想です。
…
・いつも情報提供ありがとうございます。松本先生のお話が、とてもわかりやすかったです。
・大切な部分を、具体的に説明してくれたので、会社が何をしたらよいのかがわかってよかった。
・法律の範囲内で、会社が苦しくならない程度のことをやっていこうと思いました。
・10月改正についての説明のセミナーも、参加させていただきます。
・いつもありがとうございます。おかげでよくわかりました。3月のパワハラのセミナーも申し込ませていただきます。
…
熱心にご参加いただいた皆様、ありがとうございました。
Posted in これまでのセミナー | No Comments »
1月 31st, 2022
新型コロナウイルスの影響もあり、先の見通しが難しい会社が多いと思います。この先賃金をどう決めていったらよいのかと、これまで以上にお悩みではありませんか?
限られた原資をいかに効果的に配分し、従業員のヤル気を喚起するかが、経営者の知恵のみせどころ。また、若手を採用し、定着させるためにも、今の決め方・昇給の仕方でよいのか考えてみる必要があるのでは。
講師は西遠労務協会の山口悦子、毎年人気の賃金セミナーです。
///////////////////
賃見見直しセミナー
■日時:集合=2022年3月4日(金) 13:30~15:30
ZOOM= 2022年3月18日(金) 13:30~15:30
■開催方法:集合=浜松労政会館
ZOOM=Web会議システム「ZOOM」利用
■参加費:1名様につき16,500円(税込。顧問先様は無料)
■主催:西遠労務協会
詳しい内容と参加申込書はこちら(PDF。プリントアウトしてファックスしてください)
///////////////////
主な内容
1.賃金水準
2.賃金診断とその視点
3.中小企業に合った使いやすい賃金制度の提案
Posted in セミナー開催予定 | No Comments »
1月 31st, 2022
令和4年4月1日から中小企業にも義務化される「パワーハラスメント防止措置」。このセミナーでは、10年以上の経験を積んだハラスメント防止コンサルタントが、企業経営者様・責任者様を対象に、法律改正の概要と実務対応の仕方、加えて社内のハラスメントを防ぐにはを、わかりやすくご説明します。
///////////////////
パワハラ防止セミナー
■日時:2022年3月15日(火) 13:30~15:30
■開催方法:Web会議システム「ZOOM」利用
■参加費:1名様につき11,000円(税込。顧問先様は無料)
■主催:西遠労務協会
詳しい内容と参加申込書はこちら(PDF。プリントアウトしてファックスしてください)
///////////////////
主な内容
1.何がパワハラになってしまう?
2.法改正で求められる「ハラスメント防止のために講ずべき措置」
3.ハラスメント問題が起きない会社にするために
Posted in セミナー開催予定 | No Comments »